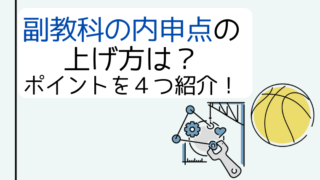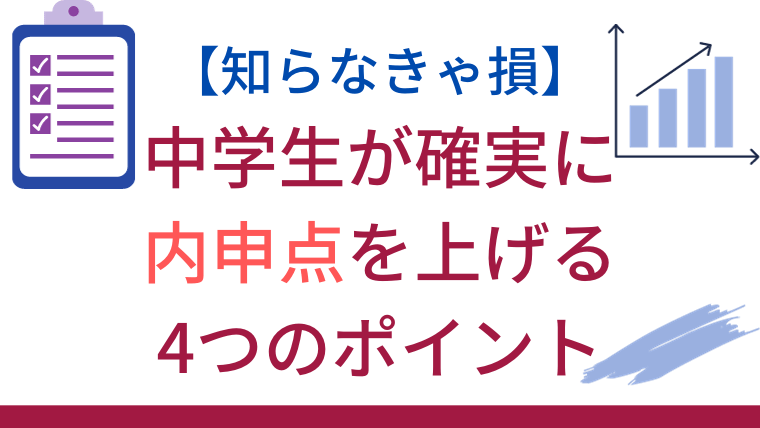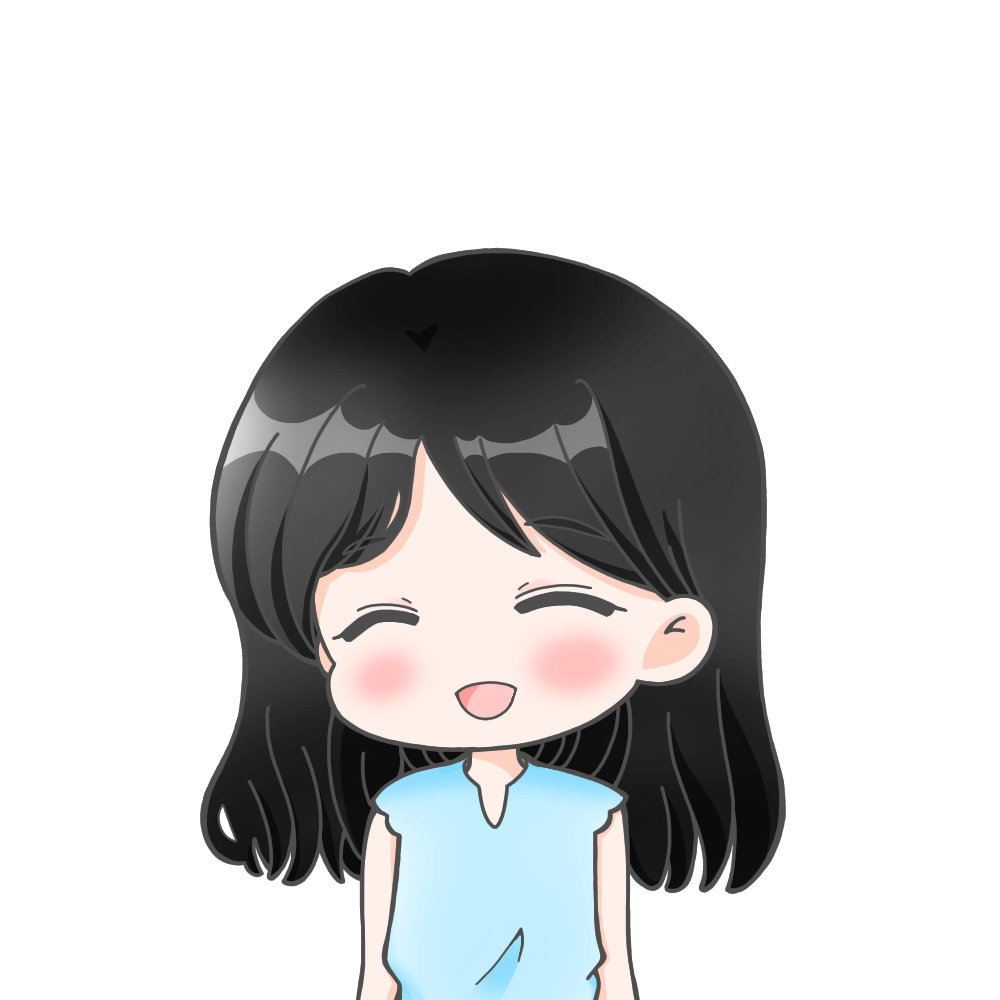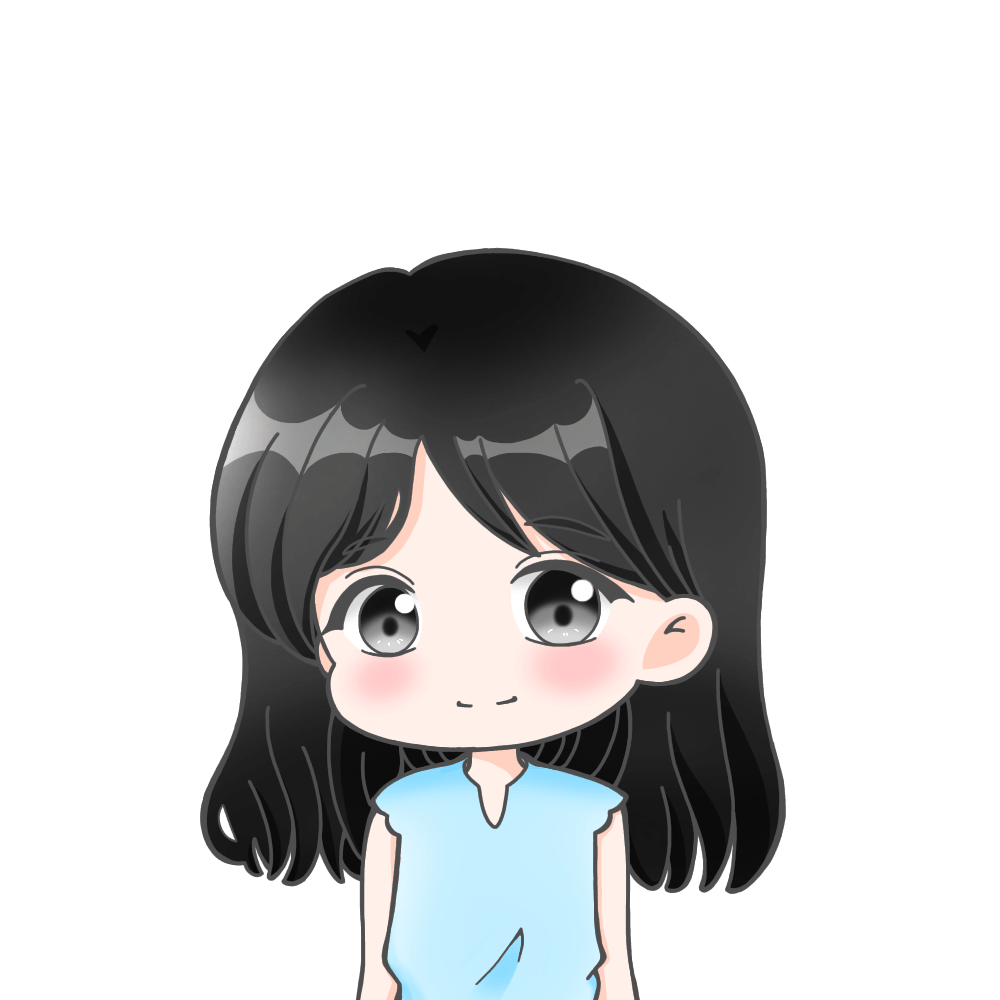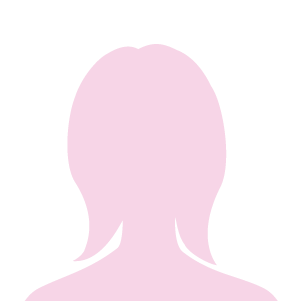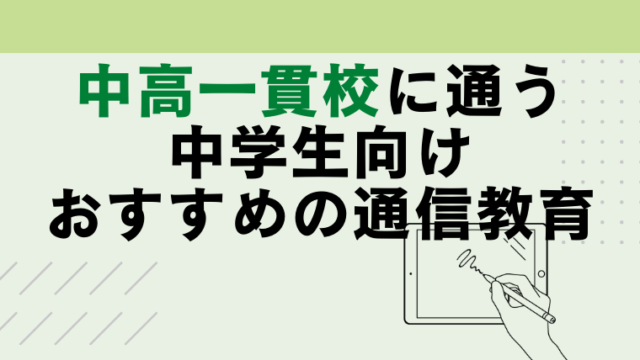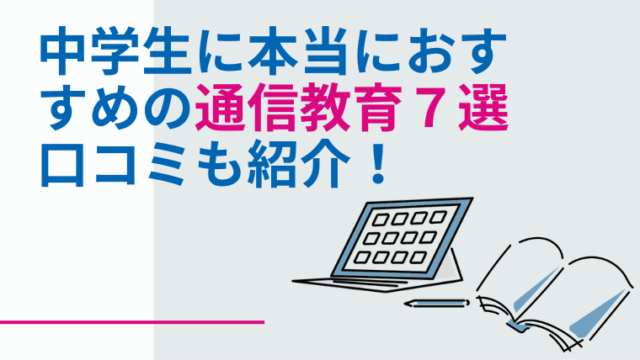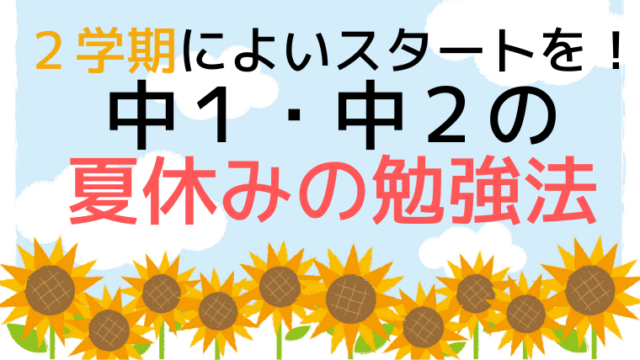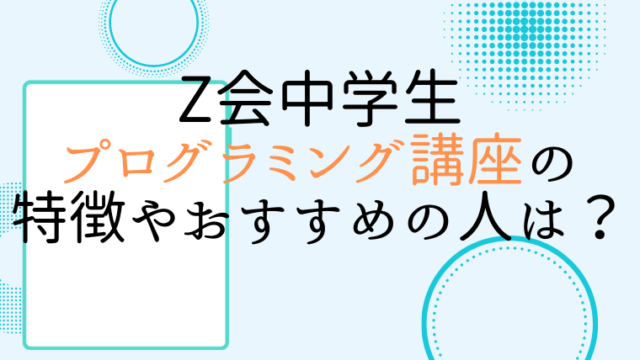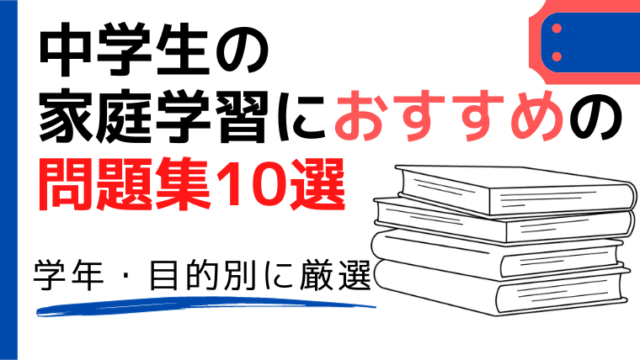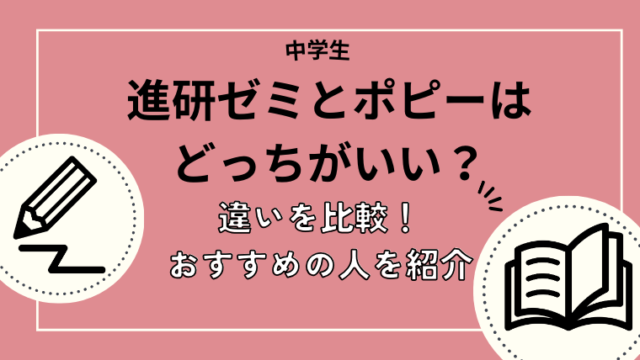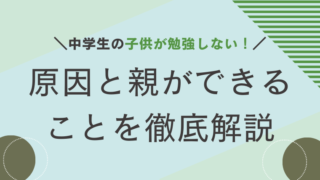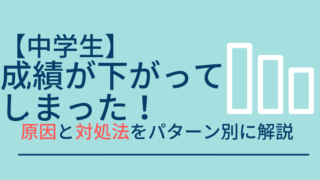この記事では、中学生が確実に内申点を上げる方法についてお話ししたいと思います。
中学生と保護者の方に役立つ情報を、わかりやすくお届けします!
中学校に入ると、よく「内申点」という言葉を聞くようになるでしょう。
内申点は通知表の評定のことです。通常1~5の5段階評価でつけます。
ところで、この内申点、どのような仕組みでつけているかみなさんご存じでしょうか?
この記事では、実際に中学校教員として内申点をつけていた私が、内申点のつけ方や内申点を上げるポイントをお教えしようと思います!
そもそも内申点とは?なぜ重要なの?

内申点は、通知表の評定のことを指します。
だいたい1~5の5段階評価です。
そしてこの内申点は、高校受験に提出する内申書にも記載されます。
各教科ごとに学期ごとに出された評定を平均したものを学年末に算出し、内申書に記載します。(5段階評価×9教科=満点45点)
内申書は、高校受験の際に受験者の学力を見るときにとても重要な役割を果たします。
しかも内申書に載る内申点は中学1年生の学年末平均のものから載るので、中学校生活全体において内申点をしっかりととる取り組みが大切です。
内申点の付け方と評価の観点

内申点を出す際には、以下の3つの観点に沿って生徒の学びの様子を見ます。
- 知識・技能 (授業で習ったことが身についているか)
- 思考・判断・表現 (筋道立てて考え自分の言葉で表現できるか)
- 主体的に学習に取り組む態度 (学びに積極的に向かえているか、広げようとしているか)
これら3つの観点をA~Cで評価し、最終的にその評価をもとに1~5の評定を出します。
テストの結果だけでなく、学びの広がりや学びへ向かう姿勢も大切!
内申点は、3つの観点を総合的に見たものになっているのが最大の特長です。
特に、「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」は定期テストや小テストの結果だけでは測ることができません。
- 自分の意見をみんなの前でわかりやすく発表できるか
- グループワークで友達の意見を聞いて自分の考えを広げているか
- 授業プリントで、その日の学びについてきちんと振り返れているか
なども、内申点を上げるうえでは重要なポイントになります。
中学生が確実に内申点を上げるための4つのポイント

中学生が内申点を上げるには、以下の4つのポイントを確実におさえるようにしましょう!
- 定期テストで点数をとる
- 小テストで点数をとる
- 提出物をしっかり出す
- 授業態度に気をつける
「内申点を上げるためにいろいろ気にしなきゃいけないの?」と不安になる方もいるかもしれませんが、まずは基本的なことを確実に行っていければOKです!
定期テストで点数をとる

中学生が確実に内申点を上げるには、定期テストで点数をとるのが最も効果的です。
定期テストができている=評価の3観点をほぼ満たしていると言えるからです。
- 知識・技能 (授業で習ったことが身についている)
- 思考・判断・表現 (記述問題等で自分の考えを筋道立てて述べている)
- 主体的に学習に取り組む態度 (テストで点数をとるために積極的に勉強している)
定期テストだけで内申点を判断はしないとはいえ、内申点を決める大きな要素となることは事実ですので、しっかり取り組みましょう!
定期テストの勉強をするときには、以下の3点に気をつけて対策しましょう。
使用する教材は、学校のワークや教科書だけでも十分に対策できますよ!
定期テストの勉強で気をつけること
- 覚えていないと解けない語句の暗記は徹底して行う
- 間違えた問題を中心に、ワークの解き直しを行う
- 副教科も内申点に入るので、手を抜かずに勉強する
定期テストの点数の上げ方や、定期テストの基本的な勉強法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
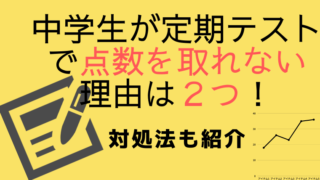
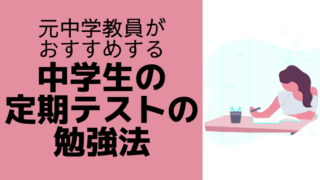
小テストで点数をとる
小テストの出来も、内申点に反映されます。
- 漢字のテスト
- 英単語のテスト
- 数学の公式テスト
- 各教科の単元テスト
せっかく定期テストの結果がよくても、小テストができていないと、定期テストの点数からマイナスして内申点をつけざるをえません。
どんなに小さな小テストでも、手を抜かずに満点をとるつもりで取り組みましょう!
提出物をしっかり出す
提出物を提出しているか、取り組み方はどうかも内申点に影響します。
- 各教科のワーク
- 各教科のノート
- 授業の感想プリント
提出物は、出したか出さないかの事実も大切ですが、もちろん内容も大切です。
- 丸付けをせずにワークを提出する
- 感想プリントを1、2行で提出する
これでは、「主体的に学習に取り組む態度」の項目で十分な評価は得られません。
クオリティの伴った提出物を出すようにしましょう!
- 問題集→丸付けして間違いを直す。できていない問題を解きなおしたり、どうしたら次間違えないかも記入する
- 授業の感想プリント→授業を学んでどう考えが変わったか、次の目標などを具体的に記入する
授業態度に気をつける
定期テストや小テストの点数がいくらよくても、授業態度がよくなければ、評定5をつけることはできません。
- 授業中の活動に積極的に参加していない (寝ている・おしゃべりしているなど)
- 提出物への取り組み方が悪い(プリントを白紙で提出など)
は、「主体的に学習に取り組む態度」が減点になりますので注意しましょう。
- 自分の意見を積極的にクラスメイトに発表する
- グループワークでみんなの意見を積極的にまとめる
- 友達の意見を聞いて、自分の考えを広げたり深めたりしている(提出物に記入)
授業中積極的に発言しないと内申点は上げられない?

内申点を上げようとしている保護者の方のなかには、お子様の授業態度の評価をよくするために
と助言する方もいらっしゃると思います。
もちろん積極的に発言するに越したことはないですが、授業態度は発言だけで測るものではなく、総合的に見ています。
たとえ積極的に発言しない子でも、回収したノートやプリントの解答などから授業への取り組み方や理解度を見ることができます。
しっかりと授業を聞き、プリント類に真面目に取り組んでいれば、授業態度でマイナスになることはありません。
発言が難しい子は、提出物を忘れずに提出し、授業プリントやノートの記述内容からアプローチしてみましょう!
自分の考えを文字でしっかり表現できれば、先生は評価してくれます。
まとめ
- 定期テストで点数をとる
- 小テストで点数をとる
- 提出物をしっかり出す
- 授業態度に気をつける
内申点を上げるためには、まず定期テストでしっかり点数をとり、小テスト・提出物・授業態度でマイナス評価をもらわないように気をつけましょう!
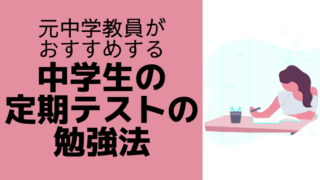
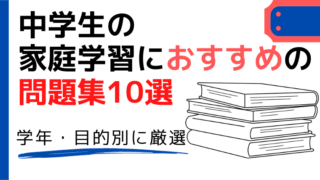
副教科の内申点の上げ方については、以下の記事もあわせてご覧ください!